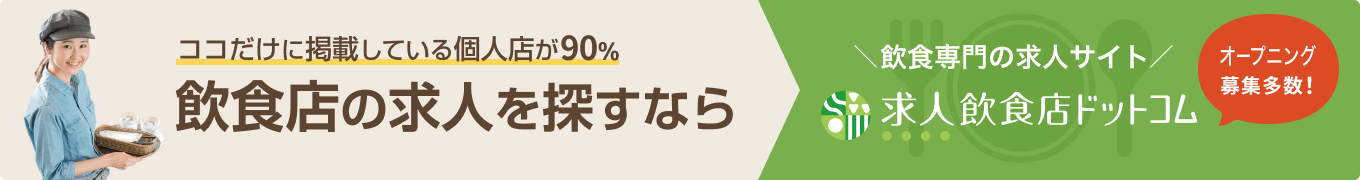初回公開日:
 Photo by iStock.com/kuppa_rock
日本では最初の一杯に「とりあえずビール」が一般的ですが、国や地域によってさまざまな乾杯の習慣があることをご存知でしょうか。せっかくお酒を扱う仕事をするなら、世界のお酒事情に精通するとさらに仕事が楽しくなるでしょう。今回は、お客様との会話に役立つお酒の小ネタや、ビールを提供する本場のお店などをご紹介します。居酒屋やバーなどお酒関係のお店で働く方々はぜひ参考にしてください。
Photo by iStock.com/kuppa_rock
日本では最初の一杯に「とりあえずビール」が一般的ですが、国や地域によってさまざまな乾杯の習慣があることをご存知でしょうか。せっかくお酒を扱う仕事をするなら、世界のお酒事情に精通するとさらに仕事が楽しくなるでしょう。今回は、お客様との会話に役立つお酒の小ネタや、ビールを提供する本場のお店などをご紹介します。居酒屋やバーなどお酒関係のお店で働く方々はぜひ参考にしてください。
 Photo by iStock.com/ViewApart
Photo by iStock.com/ViewApart
フランス人がビールを飲む印象はあまりありませんが、カジュアルに楽しまれています。多くのカフェやバーでは、夕方17時から20時ごろまでは「ハッピーアワー」といって通常の半額でビールやカクテルを提供しています。フランスの国民的ビールといえば『クロネンブルグ1664』で愛称は「セーズ」。クセがなくすっきりとした味わい、香りも程よく万人受けするビールです。
日本ではカクテルのベースになることが多いウォッカですが、本場では、小さいグラスで一気にストレートで飲むのが定番。まず「ザ・ズダロービエ(健康に)」と乾杯し全員で飲み干すと、一杯ごとに乾杯のセリフを変え次々と飲んでいきます。アルコール度数が約40%もあるので、冷凍庫で冷やしても凍らず、とろりとした口当たりになります。バーなどでゆっくりと飲むときはロックが好まれます。柑橘系と相性が良いので、ライムやレモンを添えるのもオススメです。
とはいえ若い人たちの間ではビールも人気。実はロシアでは、ビールはお酒ではありませんでした。2011年までアルコール度数10%以下は「酒類」でなく「食品」扱いだったそうです。
そして、中国は世界一ビールの消費量が多いビール大国(※)です。代表的なビールといえば『青島(チンタオ)ビール』。その起源は、世界有数のビール大国ドイツにありました。19世紀末、青島はドイツの支配下に置かれ、ドイツの技術を移転してビール造りが始まりました。今や『青島ビール』は世界で第6位のシェアを誇ります(2016年のデータ)。 ※国別消費量のこと。国別一人当たりビール消費量が最大なのはチェコ。
 Photo by iStock.com/Wavebreakmedia
Photo by iStock.com/Wavebreakmedia
ドイツのビアガーデンは、緑に囲まれた公園や広場、レストランの中庭に開かれ、まさに「ビールのガーデン」。ビールや料理はセルフサービスで、専用のカウンターで購入し、テーブルは相席です。また、ドイツのビアガーデンではビアガーデン発祥の頃からどんな階級の人でもビールが楽しめるようフードの持ち込みはOKでした。現在でもビールを楽しむ社交場として、その伝統が続いています。
多くのブルワリーでは、工場見学でテイスティングできるほか、醸造所の一角にパブを設けて、出来たてのビールが楽しめます。倉庫のような所にあるスタンディングバーや、カフェスタイルでビールだけでなく、フードも充実させるなど、ビールも個性的ですが、お店のスタイルも様々。一軒で多くの種類のクラフトビールが楽しめます。
一方、イギリスのブリティッシュパブも社交の場ですが、1人で新聞を広げるなど静かに飲みたい人はそっとしておく文化があるそうです。どちらもお酒を楽しむ空間づくりにバーマンの役割が大きいのが特徴です。
いかがでしたか。お酒の習慣はその国民性や地域性を表しており、プライベートで外国人の友人をもてなす際や海外旅行の際に知っておくと便利です。特に飲食店で働く方は、奥深い世界のお酒について知識の幅を広げて、仕事にいかしてみてください。
求人@飲食店.COMではお酒を知識が身につくお仕事をたくさん紹介しています。 ワインの知識が身につく飲食店の求人一覧、 日本酒の知識が身につく飲食店の求人一覧、 お酒(リキュール・ウィスキーなど)の知識が身につく飲食店の求人一覧よりご覧ください。
「とりあえずビール」は日本だけ? 飲食店で働く人が知っておきたい世界のお酒事情
 Photo by iStock.com/kuppa_rock
Photo by iStock.com/kuppa_rock
乾杯はビールじゃなくて○○だった
 Photo by iStock.com/ViewApart
Photo by iStock.com/ViewApart
ワインの国フランスのお洒落なワイン
ワイン大国フランスの「乾杯」は、シャンパンなどのスパークリングワインから華やかに始まります。食前に飲むお酒をアペリティフと言って、シャンパンのほかにワインベースのカクテルが好まれます。たとえば、白ワインをベースに少量のカシスリキュールを加えた「キール」。白ワインの代わりにスパークリングを加えると「キールロワイヤル」になります。お酒もグラスも良く冷やすのがポイント。爽やかで彩りも美しく、本場フランスでも女性に人気です。フランス人がビールを飲む印象はあまりありませんが、カジュアルに楽しまれています。多くのカフェやバーでは、夕方17時から20時ごろまでは「ハッピーアワー」といって通常の半額でビールやカクテルを提供しています。フランスの国民的ビールといえば『クロネンブルグ1664』で愛称は「セーズ」。クセがなくすっきりとした味わい、香りも程よく万人受けするビールです。
ロシアの乾杯はウォッカじゃない?
「ロシアといえばウォッカ」というイメージが強いですが、パーティや祝いごとでは、シャンパンやスパークリングワインで乾杯するのがポピュラーです。一般的にウォッカは男性のお酒。女性はワインを飲むことが多いそうです。日本ではカクテルのベースになることが多いウォッカですが、本場では、小さいグラスで一気にストレートで飲むのが定番。まず「ザ・ズダロービエ(健康に)」と乾杯し全員で飲み干すと、一杯ごとに乾杯のセリフを変え次々と飲んでいきます。アルコール度数が約40%もあるので、冷凍庫で冷やしても凍らず、とろりとした口当たりになります。バーなどでゆっくりと飲むときはロックが好まれます。柑橘系と相性が良いので、ライムやレモンを添えるのもオススメです。
とはいえ若い人たちの間ではビールも人気。実はロシアでは、ビールはお酒ではありませんでした。2011年までアルコール度数10%以下は「酒類」でなく「食品」扱いだったそうです。
中国はつよ~いお酒の乾杯合戦
中国では、宴会での乾杯は白酒(バイチュウ)から始まります。ひと昔前ではアルコール度が50%以上という白酒ですが、最近では度数を落とした「低度酒」という種類が主流になっているようです。アルコール度数が下がったといっても、中国で乾杯すると、注がれたお酒は全て飲み干さなければなりません。しかも、自分のペースではなく、必ず誰かと乾杯し合ってお酒を飲むのがマナーというので、アルコールに弱い方は気をつけたほうがよさそうです。そして、中国は世界一ビールの消費量が多いビール大国(※)です。代表的なビールといえば『青島(チンタオ)ビール』。その起源は、世界有数のビール大国ドイツにありました。19世紀末、青島はドイツの支配下に置かれ、ドイツの技術を移転してビール造りが始まりました。今や『青島ビール』は世界で第6位のシェアを誇ります(2016年のデータ)。 ※国別消費量のこと。国別一人当たりビール消費量が最大なのはチェコ。
ビール大国のビールなお店たち
 Photo by iStock.com/Wavebreakmedia
Photo by iStock.com/Wavebreakmedia
ここまで世界の乾杯事情についてお話しましたが、やっぱり日本人が最もよく飲むお酒といえばビール。ここではビール大国の有名店について紹介していきます。
ドイツに見る本場のビアホール、ビアガーデンとは
5000種類ものビールがあるビール王国ドイツ。ドイツで美味しいビールを飲めるお店といえば、ブラウハウス。醸造所直営のビアホールで出来たてのビールと食事が楽しめます。昔ながらのスタイルの店では、男性のウェイターが常にお代わり用のグラスを持ち、飲み終えるとすぐに次のグラスが置かれます。これ以上は飲まない、という合図はコースターでグラスにフタをします。ビールをお待たせしないためには、ドイツでも日本でも多くのグラスを持つ腕力と目配りが必要ですね。ドイツのビアガーデンは、緑に囲まれた公園や広場、レストランの中庭に開かれ、まさに「ビールのガーデン」。ビールや料理はセルフサービスで、専用のカウンターで購入し、テーブルは相席です。また、ドイツのビアガーデンではビアガーデン発祥の頃からどんな階級の人でもビールが楽しめるようフードの持ち込みはOKでした。現在でもビールを楽しむ社交場として、その伝統が続いています。
クラフトビール大国のアメリカ
いまや世界的なブームとなっているクラフトビール。そのムーブメントはアメリカの西海岸から始まり、1987年、ニューヨークの『ブルックリン・ブルワリー』の誕生がアメリカ各地に小規模なブルワリーを生み出すきっかけとなりました。多くのブルワリーでは、工場見学でテイスティングできるほか、醸造所の一角にパブを設けて、出来たてのビールが楽しめます。倉庫のような所にあるスタンディングバーや、カフェスタイルでビールだけでなく、フードも充実させるなど、ビールも個性的ですが、お店のスタイルも様々。一軒で多くの種類のクラフトビールが楽しめます。
気さくなアイリッシュパブ、大人の社交場ブリティッシュパブ
パブとはパブリックハウス(公共の家)の略で、本場アイルランドは社交の場であり生活の場所です。カウンターの中のバーマン(バーテンダー)は、気さくにお客さんとコミュニケーションを取り、初めてのお客さんを常連さんに引き合わせます。また、普段は音楽を流さないところでも、週末はライブをしたり、ダンスをするなどとても賑やか。一方、イギリスのブリティッシュパブも社交の場ですが、1人で新聞を広げるなど静かに飲みたい人はそっとしておく文化があるそうです。どちらもお酒を楽しむ空間づくりにバーマンの役割が大きいのが特徴です。
いかがでしたか。お酒の習慣はその国民性や地域性を表しており、プライベートで外国人の友人をもてなす際や海外旅行の際に知っておくと便利です。特に飲食店で働く方は、奥深い世界のお酒について知識の幅を広げて、仕事にいかしてみてください。
求人@飲食店.COMではお酒を知識が身につくお仕事をたくさん紹介しています。 ワインの知識が身につく飲食店の求人一覧、 日本酒の知識が身につく飲食店の求人一覧、 お酒(リキュール・ウィスキーなど)の知識が身につく飲食店の求人一覧よりご覧ください。